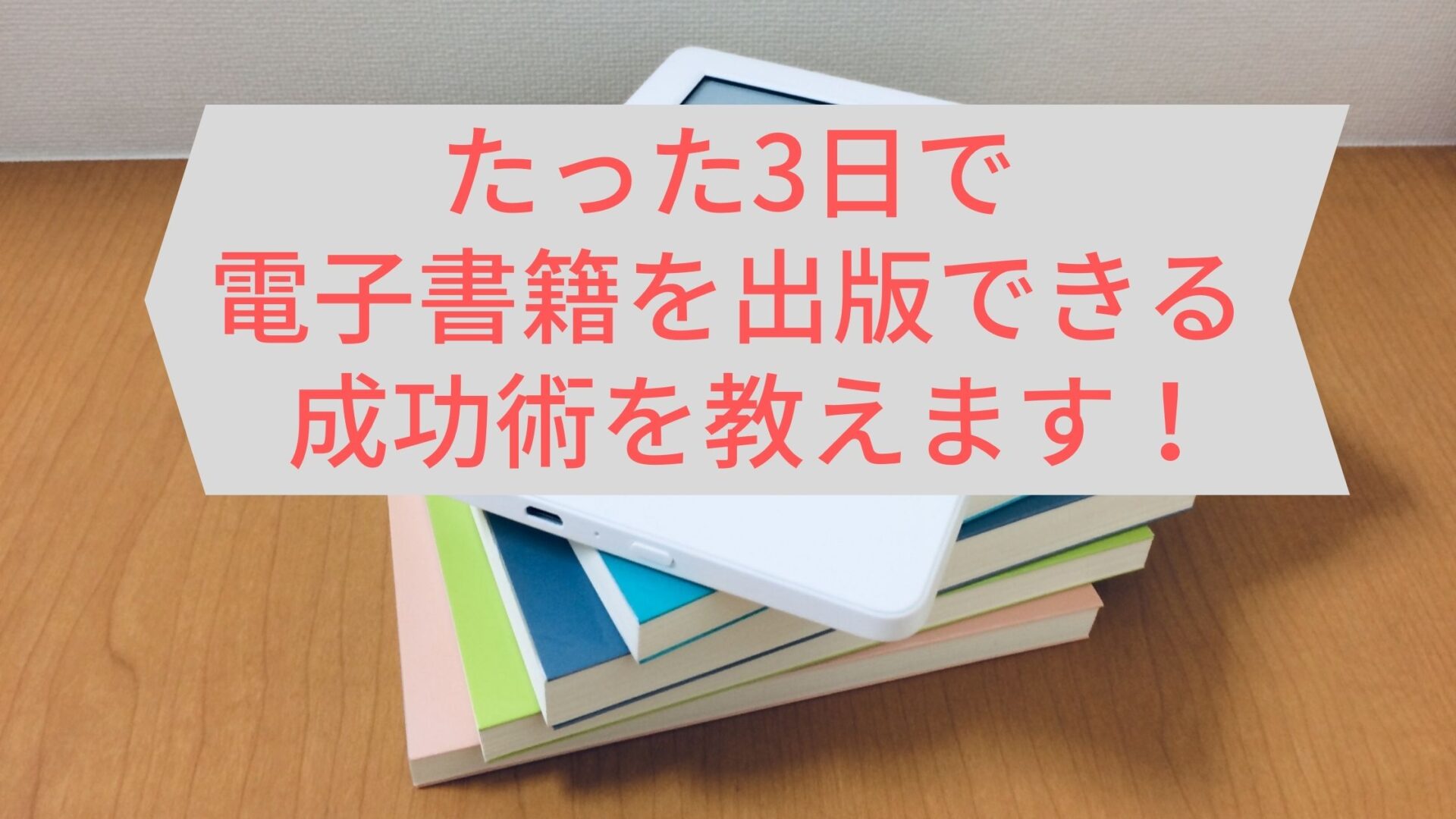自作パソコンのパーツ選びの鉄則(SSD編)

HDD(Hard Disk Drive)と比較して、機械的な駆動部分がなく、
半導体メモリなので、その速さから自作パソコンの
起動ドライブとして一般的になったSSD(Solid State Disk)です。
250GBの容量クラスで1万2000円前後、500GBクラスで
2万5000円前後と大容量モデルが買いやすくなりました。
Serial ATA 6Gbpsでは性能が頭打ちのため、より高速な接続方式が
普及しつつあります。
SSD選びの鉄則
・起動ドライブなら少なくとも120GBクラス、250GBクラスなら
余裕を持って使えます
・使い方や空き容量によって速度は変わります。
使用上の速度はビークの値です。
・一般的な使い方ならさほど気にしなくても良い。
保証期間内は使える
500GBクラスが値下がりし、買いやすくなった
M.2やMVMeなど次世代の規格の普及が進む
SSDは2.5インチHDDのサイズが主流
低価格モデルにはTLCタイプのNANDを採用したSSDも登場
NANDは電子を貯める「セル」の集合
内部処理で重要なのは、データを直接書き換えができないため、
別の領域を使って消してはいけないデータを退避して、
改めて書き込む場所にまとめる。
「ガーベージコレクション」はデータを集めて消去可能な
ブロックを作る機能で、消去しておけばすぐに書き込む領域になるため、
速度低下が防げる。
SSDは長期間使い続けると書き込み性能が低下する
SSDの寿命をのばすウェアレベリング
SSDの端子は、拡張ボード(PCI Express)、2.5インチ(Serial ATA)、MSATA、M.2の
4種類。
M.2は信号と形状の違いでさらに種類がある。
SATA 6Gbpsはすでに限界
高速モデルはPCI Express接続に移行
RAID構成で高速にしたPCI ExpressボードのSSD
より高速なM.2接続の普及が進む
MVMe対応SSDは既に登場している
PCI-E接続は最新マザーが楽
次回は、自作パソコンのパーツ選びの鉄則(HDD編)について、書きますね。