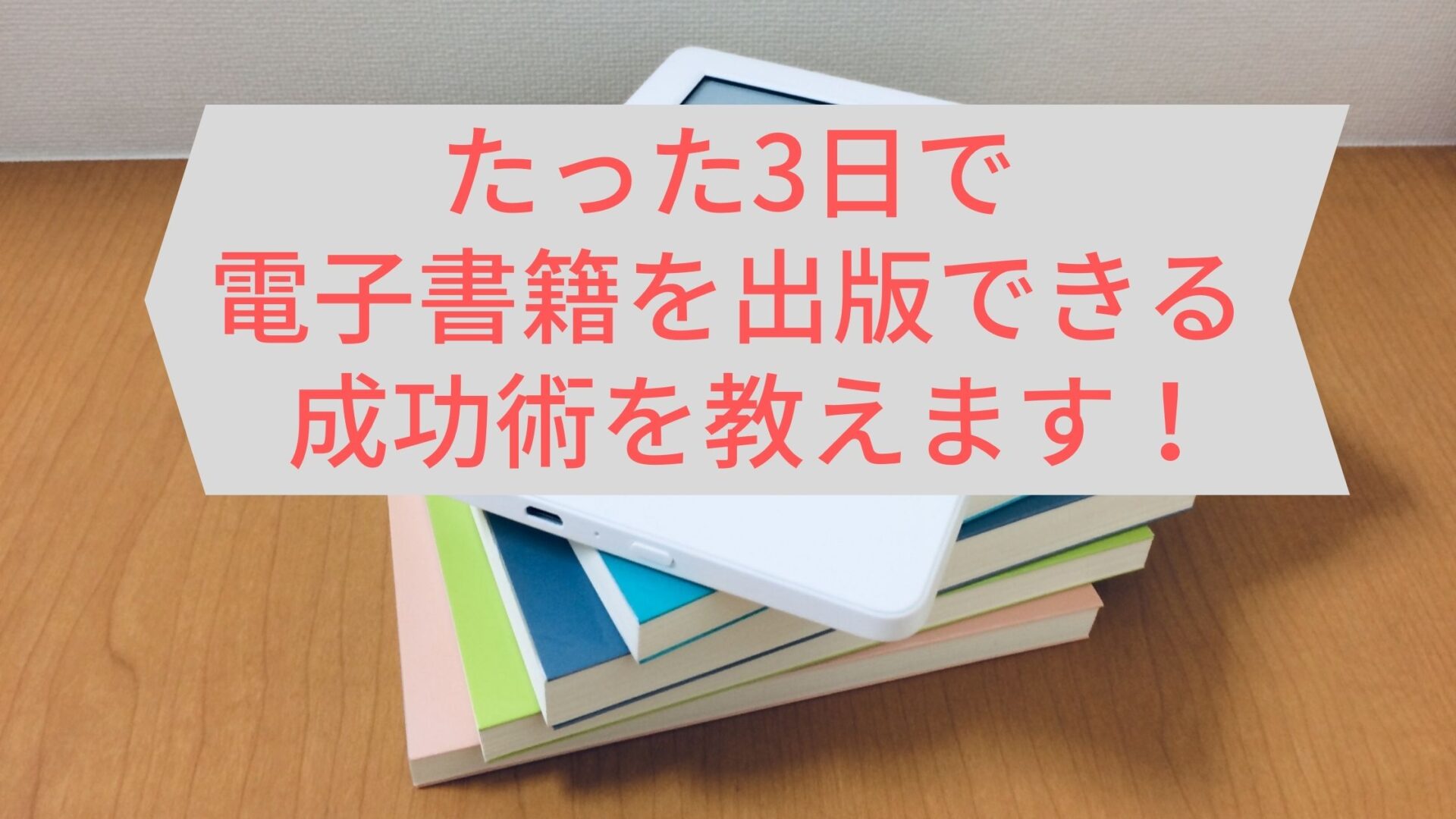運賃計算の元となる営業キロ、運賃計算キロは実際に乗る経路どおりに
計算することが原則です。しかし、原則があれば、例外もあるのが世の常。
以前ご紹介した近郊区間など、最たるものかも知れません。
JRの路線には、両者の需要がほぼ等しかったり、列車の運転の都合などに
より同じ区間であっても同等に利用できる経路が複数ある場合があります。
このうち、全国で9つの区間は「特定区間」に指定され、運賃のほか、
特急・急行料金、グリーン料金も、実際の乗車経路にかかわらず、
必ず短い方の経路で計算することとされています。
特定区間では、自動的に運賃計算がおこなわれるので、利用者は
「どちらを経由するか」を申し出る必要がありません。
そしてどちらを経由してもよく、途中下車ができるきっぷであれば、
途中下車もできます。
岩国~櫛ケ浜間における山陽本線と岩徳線(地方交通線である岩徳線の
ほうが短い)の特定区間などは、山陽新幹線の運賃計算にも影響しており、
新岩国~徳山間をとおる場合は、新幹線なのに換算キロがかかわる
運賃計算キロを使わなければなりません。
短絡線として岩徳線が建設され、一時は今の岩徳線が、山陽本線となって、
急行などが経由していたという歴史がこの区間にからんでいて、
今に至っています。
全国で9つの区間は「特定区間」(○がついている経路で計算)は、
以下に示すとおりです。
1.大沼~森(JR北海道)
○函館本線(大沼公園経由)/函館本線(東森経由)
2.赤羽~大宮(JR東日本)
○東北本線(浦和経由)/東北本線[埼京線](戸田公園経由)
3.日暮里~赤羽(JR東日本)
○東北本線[京浜東北線](王子経由)/東北本線(尾久経由)
4.品川~鶴見(JR東日本)
○東海道本線(川崎経由)/東海道本線[横須賀線](新川崎経由)
5.東京~蘇我(JR東日本)
○総武本線+外房線/京葉線
6.山科~近江塩津(JR西日本)
○湖西線/東海道本線+北陸本線
7.大阪~天王寺(JR西日本)
○大阪環状線(天満経由)/大阪環状線(福島経由)
8.三原~海田市(JR西日本)
○山陽本線/呉線
9.岩国~櫛ケ浜(JR西日本)
○岩徳線/山陽本線