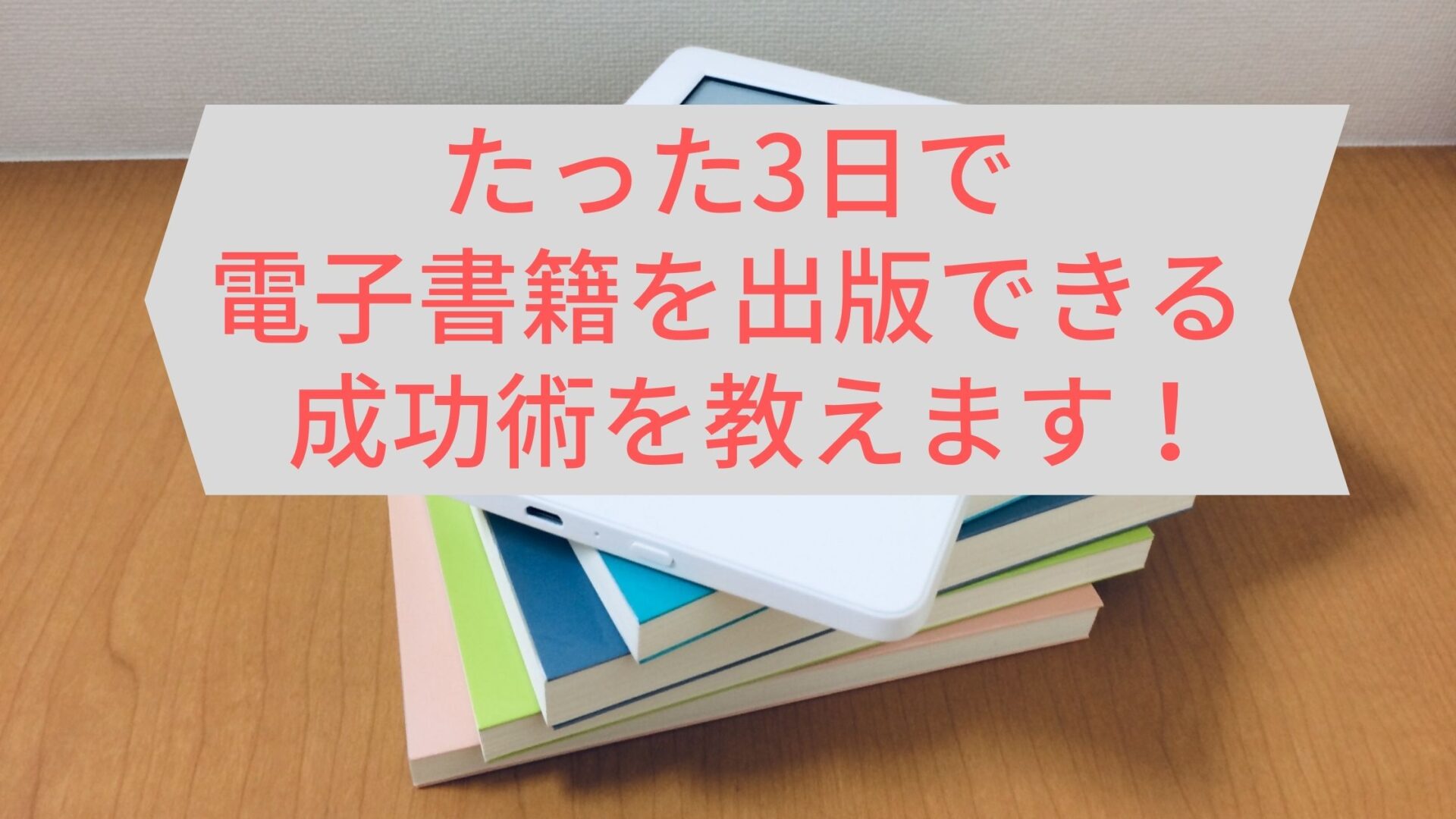1~3キロ(JR3社の幹線)の6カ月の定期運賃は
22,160円です。
1カ月の定期運賃は4,620円との関係を計算してみますと、
140円×30日×6カ月×1.1=27,720
≒27,720×0.8=22,160(6円は切り捨て)
出てきた27,720円に0.8を掛けるというのは80%、
言い換えれば2割引きであることを意味しています。
つまり1か月分の定期運賃の6倍(6カ月分)の
2割引きということです。
1~25キロまでは、
”消費税を含まない運賃×30×6カ月×0.8×1.1(消費税)”と
いう計算式で6カ月運賃は出ます。
しかし、1カ月定期の6カ月分の20%引きというのは、1~25キロまでです。
それ以上の距離では、割引率が違って、率は低くなっています。
例えば、50キロの6カ月定期運賃で見てみますと、
24,250×6カ月
=145,500×X=123,560円
X=85%(厳密にいううと84.9%)となります。
ことばを換えていえば15%引きということです。
このように26キロ以上では割引率が下がっているのです。
遠距離になれば割引率が低くなるので、
50キロのところから通う人の場合、
25キロずつ分けて買うならどうなるかといえば、
25キロの6カ月の定期運賃は60,180円、
60,180×2=120,360円です。
通しで買った50キロの定期運賃は123,560円ですので、
2つを比較すると、通しで買うより分けて買ったほうが、
3,200円安くなります。このような”現象”は、
25キロでは20%引きなのに、
50キロでは15%しか割引にならないために起こります。